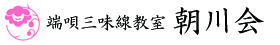「初雪」3
音子ももう一口飲んでから、ちらっと洋介を見た。
「だけどさ、洋介が着物着てくるとは思わなかった」
「あ、俺?いや、ちょっと前からさ、着物着てみようかなっていうか、なんで着物着ないのかな、なんて思ってさ、それで買ってみたんだけど、変?」
音子は、くすっと笑った。
「変じゃないよ。全然。男子の着物姿って、結構いいね」
洋介は、照れ臭くなり、小皿に盛られた松前漬けに箸を付けた。
「これ、うまいな」
「ありがとう。おばあちゃんが作ったのをもらってきたの。毎年作るんだ」
音子も一口つまんだ。
「いつかちゃんと教わろうと思ってる」
「へえ。意外に家庭的なんだな」
「意外はよけいでしょ」
音子は首をすくめて、そっぽを向いたので、珊瑚のかんざしが、ちらりと見えた。
「それにしても、音子の家がさ、浅草に近くて良かったよ」
「歩いて来れるからね」
「このあたりは、なんていうの?」
「向島」
「へえ」
洋介は東京育ちだ。でも新宿や渋谷はわかるが、向島なんて、全然知らなかった。
そういえば、器も、よく知らない。手に持ったお猪口を眺めながら音子に聞いた。
「これ、渋いよね」
「それ、備前焼。わたし、焼き物好きなんだ。どっちかっていうと、磁器より陶器が好きで、気に入ったものを、少しずつ集めてるんだ」
「へえー」
気に入ったいいものを少しずつ集めるというのが、音子らしいなと洋介は思った。洋介は、陶器と磁器の違いもよく分からない。でも、このお猪口は、安物ではない感じがする。
「俺、よくわからないけど、これはきっといいものだよね」
お猪口から目を放して洋介は聞いた。
「うん。背伸びして買っちゃった。でもいいの。一生物だから」
音子は、大事そうに徳利を持って、自分のお猪口にトクトクとお酒を注いだ。
「一生物かあ。いいなあ」
洋介は、手にしたお猪口を眺めていた。
「これで、一生飲めるやつは、幸せだな」
「え?」と思った途端、音子は、カッと耳まで赤くなった。
「暑い暑い。ちょっと酔っぱらっちゃった」
あわてて炬燵から立ち上がると窓の前へ座った。それから、小さな手で、窓の曇りを拭いて、外を見た。
「雪、すごいよ。もう道が真っ白」
「え、ほんと?」
洋介も炬燵から出て、音子の隣で大きな指で窓をぬぐって外を見た。
「ほんとだ。すげえ」
また、洋介と触れる位に近くになった、音子は恥ずかしくて、じっと窓の外を見ていた。
通りには人通りもなく、すべての音は雪に吸い込まれたように静かだった。
「あれ、何か聞こえる」
洋介がふっと顔を上げた。
降る雪を縫うように、ポツン、ポツンと何かの音が聞こえてくる。
「何の音?」
耳を澄ました音子は、すっと顔を上げた。
「三味線」
「三味線?」
「うん。この辺りね、芸者さんがいるから、時々、聞こえるの」
「へえ・・・」
洋介は、三味線の音を聞くのは、初めてだった。
だんだん白く覆われていく街並みに、遠くから三味線の音が流れてくる。
「あ、唄ってる」
「初~雪~に」
今日は、初雪だ。
「降り込め~られ~て 向島」
二人は、並んで三味線を聞いていた。
雪は、静かに静かに降り積もっていった。
初雪
初雪に 降り込められて向島
二人が中に 置炬燵
酒の機嫌の 爪弾きは
好いた同士の 差し向かい
嘘が浮世か 浮世が実か
誠比べの 胸と胸