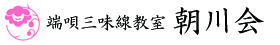勤め人にはなりたくない
私の集落は、子供の頃は、ほとんどが農家だった。その農家のおじさんたちが、よく言っていた言葉に、「勤め人にはなりたくない」というものだった。
子供心に、私は不思議だった。私の父は高校教師だった。毎日学校へ通う勤め人である。それを私は、特になんとも思っていなかったので、それがなりたくない職業だとは、なんでだろうと思っていた。小学校の頃は、冬は結構出稼ぎに行く人が多かった。文集も、出稼ぎに行く作文が多かった。「お父さんが冬もいていいな」と友だちには言われていた。でも、その子のお父さんたちは、「勤め人にはなりたくない」と言う。
この長年の不思議が、消えたのはつい最近だ。
幕末の日本を訪れた外国人たちの見た日本をまとめている「逝きし世の面影」の中に見える日本人の陽気さ、満足感、幸福感について、田中優子は、「江戸時代の人に現代人が学ぶべきもの」として、「「正々堂々と異議を唱える」姿勢」と書いている。
そうだ、これなのだ。近所の寄り合いなどで、正々堂々と政治や社会について意見を述べ合っていた大人たちを覚えている。いつも田んぼや庭先で仕事をしていた姿しか知らなかったから、びっくりしたものだ。
自分たちの食べ物は自分たちで作っている、冠婚葬祭も自分たちだけでできる、小屋や家だって自分たちで作れる人たちなのだ。集落の行事も自分たちで行うし、年齢別、性別の組織もあって、お互いに気配り目配りしあっている。自分たちの足で立って生活している。誰の顔色も伺わなくて良い。こんな安心感があるだろうか。
「勤め人」になれば、自分たちの手にしているものが、何か欠けてしまうのだ。
今は兼業農家がほとんどになってしまったけれど、集落には、まだまだ「正々堂々」としている人生の先輩はいる。その安定感のある姿、言動に、時々私はこっそり見惚れているのだ。