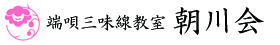「初雪」2
「せまいとこだけど、どうぞ」
下駄を脱いだ音子は、奥の六畳間に入り、エアコンと炬燵の電源を入れた。
「ああ、寒い、寒い。こっちへ入って」
音子に言われるままに、洋介はストールを取りながら、のっそり入ってきた。
「和室かあ」
「わたし、おばあちゃんちで育ったから、畳の部屋の方が、落ち着くんだ。田舎のね、大きな家でね、広い座敷がいくつもあって、囲炉裏もあった」
台所でお湯を沸かしながら、音子は言った。
「ふうん」
洋介はどっかりと腰を下ろすと炬燵に入り、両ひじを炬燵に乗せて腕を組んだ。
「なんか、いいなあ。炬燵」
「そう?よかった。わたしね、炬燵が好きなんだ。おばあちゃんち炬燵だったし」
台所から、かちゃかちゃと茶碗の音がしていた。
雪で冷えた足が、だんだん温まってきた洋介は、背中を丸めて炬燵にあたりながら、見るともなく部屋の様子を眺めた。ちょっと古めかしい茶箪笥や本棚があり、必要なものが、こじんまりと置かれた、こざっぱりとした部屋だった。
音子みたいな部屋だな、と洋介は思った。
「おまたせ」
明るい声で音子は入ってくると、備前焼の徳利とお猪口を炬燵の上に置き、「さあて」と言いながら洋介の向かいに座った。
「あけましておめでとう」
「今年もよろしくな」
二人は乾杯した。
一気に飲みほした洋介は、
「うまい、これ」
とつぶやいた。
「でしょ?これ、地元で評判の地酒なの」
自慢げに言ってから、音子は、洋介に注いだ。
「そっか、音子は雪国育ちだもんな。うまい酒あるよな」
洋介は、もう一口、うまそうに飲んだ。
二人は大学のサークルの友達だ。今日は、二人で初詣に行こうということになり、浅草に行ったのだった。背の高い洋介は、運動部らしいがっしりした体型で、モジャモジャの髪に、溶けた雪が、まだ光っていた。小柄な音子は、今日は髪を頭のてっぺんでまとめて、小さな珊瑚のかんざしを差していた。
(つづく)